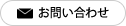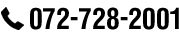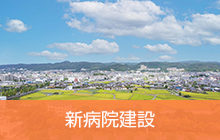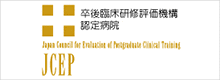医師の教育・研修
箕面市立病院HOME > 当院の特色 > 医師の教育・研修
- 臨床研修指定病院
- 卒後臨床研修評価機構(JCEP)
- 臨床研修プログラム
- 後期研修プログラム
- 医学生の教育
-
当院は臨床研修指定病院です
医師は、医師免許を取得した後、研修医として、2年間の臨床研修をおこないます。
当院は、厚生労働省が指定する臨床研修病院として、医療福祉に貢献できる人材を育成するという役割のもと、積極的に研修医の育成を行っています。
患者さまの診療の際には指導医による指導のもとで研修医が携わらせていただくことがあります。また、研修医の他に、医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士などの医療従事者をめざす大学や専門学校の学生実習を受け入れております。
地域医療への貢献のため、趣旨をご理解いただき、皆様のご協力をお願い申し上げます。箕面市立病院の臨床研修理念
当院の理念「地域の人々の健康を支え、安らぎのある環境の中で、患者中心の、安心安全で質の高い医療を提供します。」のもと、医師としての人格を涵養し、医学および医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において適切に対応できる基本的な診療能力を身につけることを目的とします。
臨床研修基本方針
1. 医師としての基本的価値観の醸成
- 医師として必要な、「社会的使命と公衆衛生への寄与」、「利他的な態度」、「人間性の尊重」、「自らを高める姿勢」の基本的価値観を醸成します。
2. 医師としての使命の遂行に必要な資質・能力の習得
- 一般外来、病棟、初期救急、地域医療などの診療現場で、基本的な診療ができる能力を習得します。
- 診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に対応できる能力を習得します。
- 最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する問題に対して、科学的根拠に経験を加味して解決を図る問題対応能力を習得します。
- 臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行える技能を習得します。
- 患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築けるコミュニケーション能力を習得します。
- 医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図るチーム医療が実践できる能力を習得します。
- 患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮できる能力を習得します。
令和5年12月18日
-
卒後臨床研修評価認定
卒後臨床研修評価機構の認定を受けました。
認定期間:2024年3月1日から4年間
2020年1月31日NPO法人卒後臨床研修評価機構による卒後臨床研修評価機構の審査を受けました。
審査結果
当院は熱心な指導医による指導体制が構築されており、研修医の満足度は非常に高いものがある。と良い評価をしていただきました。
これを契機に、引き続き臨床研修病院としての質の向上を図り、より良い医師の育成に寄与できるよう努力してまいります。
卒後臨床研修評価とは
国民に対する医療の質の改善と向上をめざすため、臨床研修病院における研修プログラムの評価や研修状況の評価を行い、臨床研修病院のプログラムの改善、よい医師の養成に寄与することを目的としており、第3者のサーベイヤーが書類審査と訪問調査によって評価するものです。
-
臨床研修プログラム
1.名称
箕面市立病院臨床研修プログラム
箕面市立病院臨床研修広域連携型プログラム募集定員(2026年採用)
箕面市立病院臨床研修プログラム:4名
箕面市立病院臨床研修広域連携型プログラム:1名2.研修期間
2026年4月1日から2028年3月31日まで(2年間)
3.カリキュラム
1年目から2年目:内科7ヶ月、外科2ヶ月、小児科1.5ヶ月、産婦人科1.5ヶ月、麻酔科1ヶ月、整形外科1ヶ月
救急部門は、救急科で日勤帯の1ヶ月間外来研修を行い、2年目の修了時まで週0.5日の日勤帯と、並行研修を継続します。
2年目:地域医療1ヶ月、精神科1ヶ月、自由選択科7ヶ月
※広域連携型プログラムでは、1年目の1月から2年目の6月までの24週間を連携先病院で研修を行う。
研修科は、各病院において研修可能な診療科とする。4.プログラムの概要・内容
5.当院での臨床研修プログラム策定について
当院での臨床研修プログラムについては、臨床研修管理委員会での以下の意見を踏まえて策定いたしました。
1.1年目から2年目
内科7ヶ月、外科2ヶ月、小児科1.5ヶ月、産婦人科1.5ヶ月、麻酔科1ヶ月、整形外科1ヶ月、救急部門1ヶ月以上
- 初期研修では外科的な処置ができることが望ましいと考えられますので外科を2ヶ月必修としました。
- 麻酔科は気管内挿管の手技や全身管理の習得のため1ヶ月を必修としました。
- 当院での救急部門の研修は、救急診療において、指導医の元で日勤帯での1ヶ月間の研修と、他科を研修中に月3〜4回のER日・当直を2年間通年で行います。継続した並行研修により、研修修了までに基本的手技や診療技能を身につけ、適切な救急対応が行える能力を習得します。
- 救急診療では骨折などの外傷患者も多いため、外傷外科の位置づけで整形外科を1ヶ月必修としました。
- 小児救急の拠点となる豊能広域こども急病センターが当院に隣接しており、一般小児科とあわせて救急小児科分野の研修もできるよう小児科を1.5ヶ月必修としました。
- 産婦人科は、分娩と婦人科疾患を幅広く経験できるよう1.5ヶ月必修としました。
2.2年目
地域医療1ヶ月、精神科1ヶ月、選択7ヶ月
- 地域医療は箕面市内を中心とする診療所で合計1ヶ月間の研修を行います。
- 精神科は、当院に閉鎖病棟がないため、協力病院での1ヶ月の研修により、到達目標を達成します。
- 自由選択科は、すべての診療科から希望の科を選択できます。選択科目数、選択期間に制限はありませんが、研修時期は希望診療科と調整のうえ、決定します。
(選択例)
①麻酔科2ヶ月、内科1ヶ月、外科1ヶ月、眼科1ヶ月、皮膚科1ヶ 月、放射線科1ヶ月
②内科2ヶ月、外科3ヶ月、小児科2ヶ月
プログラムに関する質問は、電子メールでお送りください。
6.協力病院等
協力病院
箕面神経サナトリウム、ためなが温泉病院、川西市立総合医療センター
(広域連携型プログラム)釧路赤十字病院、長野市民病院
協力施設(変更になる可能性あり)
池尻医院、笠原小児科、くさかクリニック、箕面レディースクリニック、おおさか往診クリニック、千里ペインクリニック、箕面市介護老人保健施設
7.特色
- 2年間を通して、救急診療を経験することにより、幅広い診療能力が身に付きます。
- 電子カルテの採用により、職種間の情報共有が容易です。
- NST(栄養サポートチーム)、ICT(感染対策チーム)などの病院ラウンドに参加し、EBM(根拠に基づく医療)に則った研修を受けることができます。
8.初期研修医の主な出身大学
大阪大学、大阪医科薬科大学、関西医科大学、大阪公立大学、近畿大学、兵庫医科大学、滋賀医科大学、広島大学、鳥取大学、福岡大学、産業医科大学、山梨大学、群馬大学
9.臨床研修管理委員会設置要綱
当院での臨床研修の実施にあたり、研修医の採用、評価等の管理について審議する委員会です。
臨床研修管理委員会設置要綱.pdf(PDF:99KB) -
後期研修プログラム
-
医学生の教育
箕面市立病院で求められている医療を高い水準で行うためには、資質の高い医療従事者の育成が必要不可欠です。当院は大阪大学、関西医科大学、兵庫医科大学と学外臨床実習の協定を締結しております。それぞれの大学の5年次、6年次の学生に対して各々1-3週間の臨床実習を当院で行っております。
医学教育における重要な課題として臨床実習の充実があります。新しい実習方法として単なる見学ではなく、医学生が病棟に所属し医療チームの一員として、実際に患者の診療に携わる臨床実習の形態で行う方法「クリニカル・クラークシップ」が導入されています。「クリニカル・クラークシップ」の実施にあたって、指導医確保のために導入されたのが臨床教授制度です。各大学が、学外の病院の医師に対して、学生教育を託すに相応しい見識と実績をもつと判断した指導医に臨床教授・臨床准教授の称号が付与されます。
箕面市立病院の臨床教授
大学名 氏名 診療科 付与の期間 大阪大学 中原 征則 消化器内科 令和6年4月1日~令和8年3月31日 大阪大学 足立 和繁 産婦人科 令和6年4月1日~令和8年3月31日 大阪大学 岡 義雄 外科 令和7年4月1日~令和9年3月31日 大阪大学 李 勝博 整形外科 令和7年4月1日~令和9年3月31日 関西医科大学 田中 一成 リハビリテーション科 令和6年4月1日~令和9年3月31日 箕面市立病院の臨床准教授
大学名 氏名 診療科 付与の期間 大阪大学 井端 剛 糖尿病・内分泌代謝内科 令和6年4月1日~令和8年3月31日 大阪大学 長谷川 泰浩 小児科 令和6年4月1日~令和8年3月31日